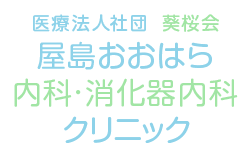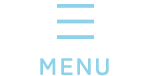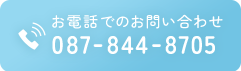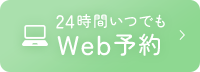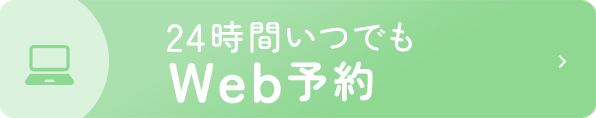日本人の100人に1人が感染しているB型肝炎
 B型肝炎ウイルス(HBV)が、血液や体液を介して体内へと侵入して肝臓へと感染し、肝炎を引き起こす病気です。
B型肝炎ウイルス(HBV)が、血液や体液を介して体内へと侵入して肝臓へと感染し、肝炎を引き起こす病気です。
ワクチン接種により感染を予防することが可能です。
健康状態や感染した時期によって、ほぼ生涯にわたり感染が継続する「持続感染」と一時的な感染に終わる「一過性感染」に分かれます。
肝炎が持続すると、性肝炎から肝硬変、さらには肝がん(肝細胞がん)へと進展する可能性があります。
B型肝炎ウイルスの感染者数は、全世界で、約3億5,000万人とされており、日本では、推定約130〜150万人(およそ100人に1人)の感染者がいるとされています。
B型肝炎の症状と潜伏期
潜伏期
感染した直後には、ほとんどの方で症状は出現しません。
潜伏期は60日〜150日とされており、平均して90日です。
しかし、中には、初期の症状として倦怠感や食欲低下などの症状が1週間程度続いた後、腹痛や黄疸(皮膚や眼球の白い部分が黄色くなること)、嘔吐などの典型的な症状が出現する方もいます。
場合によっては関節痛、関節炎、紅斑などの症状が出現することもあります。
急性肝炎
潜伏期間を経て、発熱や咽頭痛などの風邪症状、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、食欲不振、倦怠感などが出現します。
黄疸の症状が出てきた場合、激しい肝炎となる(劇症化)ことで肝不全へと進行し、命に危険が及ぶことがあります。
劇症化に至らなければ、多くの場合肝炎は数週間で極期を過ぎ、回復過程に入ります。
慢性肝炎
6ヶ月以上持続している肝炎で、症状がないことも多いですが、全身の倦怠感や疲れやすさ、食欲不振などの症状が出現することもあります。
B型肝炎の原因は?感染経路は性行為でも?
B型肝炎は、B型肝炎ウイルス(HBV)が含まれている血液や体液が体内に侵入し、感染することで起こります。
感染経路には、出産時の母から子への母子感染や性行為による感染などがあり、以下のようなものがあります。
| 垂直感染 | 出産時の母から子への母子感染 |
|---|---|
| 水平感染 |
など |
B型肝炎の検査と診断
B型肝炎と診断するには、肝炎がB型肝炎ウイルスによるものと診断するため、検査による診断確定が必要です。
血液検査
 B型肝炎ウイルスの外側の蛋白質である「HBs抗原」を検出する検査を行います。
B型肝炎ウイルスの外側の蛋白質である「HBs抗原」を検出する検査を行います。
ただし、 B型肝炎ウイルス精密検査は感染機会から35日、即日検査は感染機会より2ヶ月経過後から検出可能になります。
感染の機会から期間をある程度空けなければ検出できませんので、注意が必要です。
| HBs抗原が「陰性」の場合 | B型肝炎ウイルスへの感染は認められせん HBs抗原が陽性化するまでの期間である場合や持続感染患者の陰性化に相当する時期であった場合、陰性となることもあります 今回検査した日時を把握しておき、検査後に自覚症状などの出現があれば、再検査や医療機関の受診をしてください |
|---|---|
| HBs抗原が「陽性」の場合 | B型肝炎ウイルスに感染が認められるため、医療機関を受診していない場合は専門医による診察を受けましょう 医療機関にて、現在の感染状態を確認するため、さらに詳しい検査を実施します |
超音波検査
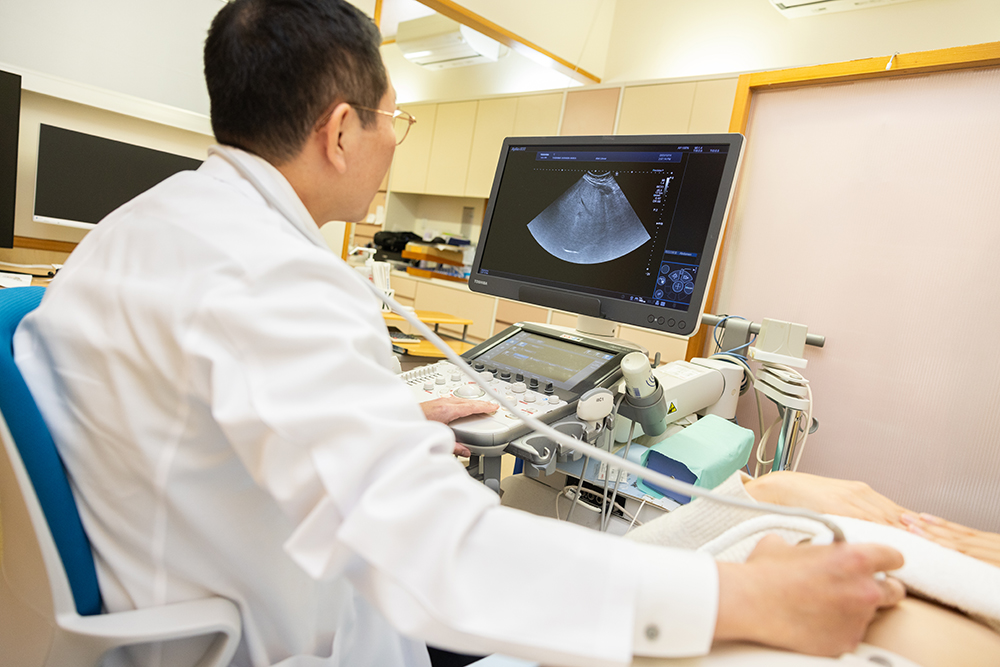 B型肝炎であると診断された場合、たとえ自覚症状がなくても肝臓がんを早期発見するために、定期的に超音波検査を受ける必要があります。
B型肝炎であると診断された場合、たとえ自覚症状がなくても肝臓がんを早期発見するために、定期的に超音波検査を受ける必要があります。
どのくらいの期間毎に検査を受けるかは、状態によります。
担当医師に相談して、検査の間隔を決めましょう。
家族に肝臓病がいたら検査を
もし、兄弟姉妹や親類に肝臓病の方がいる場合は、母子感染の可能性もあることから、血液検査を受けることをおすすめします。
B型肝炎の治療
B型肝炎には、急性B型肝炎と 慢性B型肝炎があり、それぞれ治療方法が異なります。
以下でそれぞれの治療方法を説明します。
B型肝炎は治る?
慢性B型肝炎
B型慢性肝炎の場合、持続感染しているウイルス体から完全に排除することは、現在の医療では不可能です。
そのため治療では、ウイルスの量を抑えて発がんや肝硬変への進展をさせないことを目的に行います。
治療には以下のようなものがあります。
| 治療方法 | 概要 |
|---|---|
| 抗ウイルス療法 (核酸アナログ製剤) |
内服することで、直接ウイルスに作用してウイルスの増殖を抑制し肝炎を鎮静化します。 |
| 肝庇護療法 | 肝庇護療法ではウイルス量は減少しませんが、肝炎を抑えられます。 代表的な治療薬は、内服薬のウルソデオキシコール酸と注射薬のグリチルリチン製剤です。 これらの薬剤がどうようなメカニズムで肝細胞を保護するのかはわかっていませんが、いずれの薬剤も軽度の慢性肝障害に対してはある程度有効です。 |
急性B型肝炎
基本的には、自然にHBVが排除されるのを待ちます。
ただし、非常に強い肝炎である「劇症肝炎」が起こり、放置により命の危険が予想されることもあります。
このような場合には、ウイルスの増殖を阻害する「核酸アナログ製剤」の投与、血液浄化のための血漿交換、血液透析などの肝臓の機能を補助する特殊な治療を実施することもあります。
それでも肝炎の進行が抑制できない場合には、肝移植でなければ救命が困難となるケースもあります。
B型肝炎の予防法
性行為を行う際は、コンドームを着用しましょう。
また、コンドームの使用によって完全に感染を防げるわけではないため、不特定の人との性行為は避けてください。
また、不衛生な場所での皮膚穿孔を避けることや医療器具が汚染されている可能性がある国で医療機関を受診する際には、安全とされる医療機関を受診するなど可能な限りの対策をすることも大切です。
もし、感染リスクが高いとされる地域に渡航する場合は、事前にワクチン接種を受けることも考えておきましょう。
B型肝炎ワクチン
 B型肝炎には、C型肝炎と違いワクチンがあります。
B型肝炎には、C型肝炎と違いワクチンがあります。
日本では、2016年10月から0歳児全員へのワクチンによる予防接種が実施されています。
また、医療従事者などの希望者へのワクチン接種 やB型肝炎ウイルスに持続感染している母親から出産時に感染することを防ぐために、HBV免疫グロブリンとワクチン接種の組み合わせによる予防が行われています。