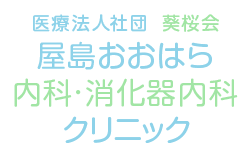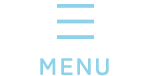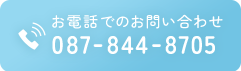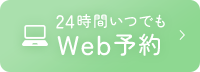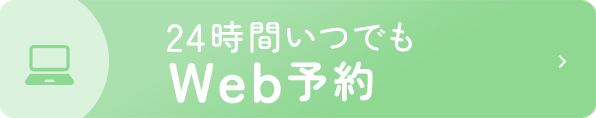過敏性腸症候群とは
 過敏性腸症候群(irritable bowel syndrome:IBS)は、お腹の痛みや調子がわるく、便秘や下痢などのお通じの異常(排便回数や便の形の異常)が長期間にわたって続く状態のときに考えられる病気です。その場合、大腸に腫瘍や炎症などの病気がないことが前提になります。
過敏性腸症候群(irritable bowel syndrome:IBS)は、お腹の痛みや調子がわるく、便秘や下痢などのお通じの異常(排便回数や便の形の異常)が長期間にわたって続く状態のときに考えられる病気です。その場合、大腸に腫瘍や炎症などの病気がないことが前提になります。
およそ10%程度の人がこの病気であるといわれている、よくある病気です。女性のほうが多く、受験時期に重なる中学生や高校生に多く、年齢とともに減ってくると言われていますが、ストレス社会の現代において年齢幅は拡がりつつあると言っても差し支えありません。
命に関わる病気ではありませんが、お腹の痛み、便秘・下痢、不安などの症状のために日常生活に支障をきたすことが少なくありません。排便によって症状がやわらいだり、排便の回数が変わり(増えたり減ったりする)、症状とともに便の形状(見た目)が変わる(柔らかくなったり硬くなったりする)などがあれば、この病気の可能性があります。
過敏性腸症候群の原因
 過敏性腸症候群の原因として考えられるのは、やはりストレス。その他に過剰な腸の働き、腸の「知覚過敏」、不規則な生活習慣などが指摘されていますが、未だはっきりとは解明されていません。しかしストレスは自律神経(興奮とリラックスをつかさどる神経)のバランスが崩れることにより、腸の動きのリズムが崩れ、腹痛や便意の異常(下痢・便秘)などの症状を引き起こします。
過敏性腸症候群の原因として考えられるのは、やはりストレス。その他に過剰な腸の働き、腸の「知覚過敏」、不規則な生活習慣などが指摘されていますが、未だはっきりとは解明されていません。しかしストレスは自律神経(興奮とリラックスをつかさどる神経)のバランスが崩れることにより、腸の動きのリズムが崩れ、腹痛や便意の異常(下痢・便秘)などの症状を引き起こします。
過敏性腸症候群はストレスが主な原因とされているため、その症状には『出やすい状況』があるといわれています。 それは、ストレスや緊張を受けやすかったりする場面です。仕事中、会議中、面接中、授業中、テスト中、出社中、登校中等がなどに症状(主に午前中)が強くなります。また、細菌やウイルスが原因となった腸炎にかかり、治ったあとに過敏性腸症候群になりやすいと言われています。
過敏性腸症候群の診断
 甲状腺機能異常症などの内分泌疾患などが症状の原因となる場合もあり、血液検査などを行います。その他、炎症所見や貧血があれば他の病気が疑われるため、大腸内視鏡検査なども必要に応じて行います。加えて症状に応じて、腹部超音波検査、腹部CT検査などを検討します。それらの検査結果と問診から総合的評価を行います。
甲状腺機能異常症などの内分泌疾患などが症状の原因となる場合もあり、血液検査などを行います。その他、炎症所見や貧血があれば他の病気が疑われるため、大腸内視鏡検査なども必要に応じて行います。加えて症状に応じて、腹部超音波検査、腹部CT検査などを検討します。それらの検査結果と問診から総合的評価を行います。
過敏性腸症候群の治療
生活習慣の改善が第一ですが、内服薬による治療を行います。薬としては、消化管機能調節薬と呼ばれる腸の運動を整える薬や、プロバイオティクス(ビフィズス菌や乳酸菌など善玉菌)、また便の水分バランスを調整する薬があります。これらは下痢症状・便秘症状が中心の患者さんのどちらにも用いられます。下痢型の方には腸の運動異常を改善させるセロトニン3受容体拮抗薬(5-HT3拮抗薬)、便秘型の方には便を柔らかくする粘膜上皮機能変容薬も用いられます。また下痢に対しては下痢止め、お腹の痛みには抗コリン薬(おなかの動きを和らげる薬)、便秘に対しては下剤も補助的、頓服的に使っていきます。
腹痛の改善には桂枝加芍薬湯、便秘型による疼痛には大建中湯(漢方薬)が広く用いられています。ストレスが高じてうつ症状が強い場合、抗うつ薬を用いますが、通常よりも少ない量で効果がみられることが多いです。精神的な問題と隠れている病気との問題で、何科を受診すればよいか分からない患者さんも多いかと思いますが、おなかの病気であることが根本なので、消化器内科受診をお勧めします。
当院では、画一的な内容ではなく患者様の生活環境や病状に合わせて治療を進めていきます。気になる症状のある方は、お気軽に当院にまでご相談ください。