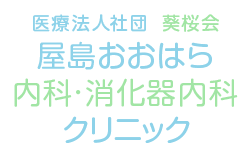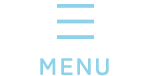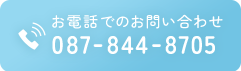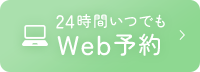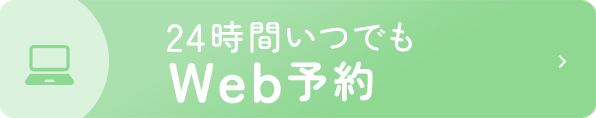- 中年以降の女性に多い自己免疫性肝炎(AIH)
- 自己免疫性肝炎に初期症状はある?
- 自己免疫性肝炎の原因
- 自己免疫性肝炎になりやすい人
- 自己免疫性肝炎の検査と診断基準
- 自己免疫性肝炎の治療
- 自己免疫性肝炎の食事の注意点
- 自己免疫性肝炎は完治する?寿命は変わる?
中年以降の女性に多い自己免疫性肝炎(AIH)
何らかの原因で自分の体内の免疫が自らの肝細胞を破壊してしまう自己免疫疾患です。
男女比は1:4と女性に多くみられ、特に中年女性が発症の中心になっています。
ただし、小児や若い女性での発症も珍しくはなく、近年の傾向として男性の罹患が以前よりも増加してきています。
自己免疫性肝炎に初期症状はある?
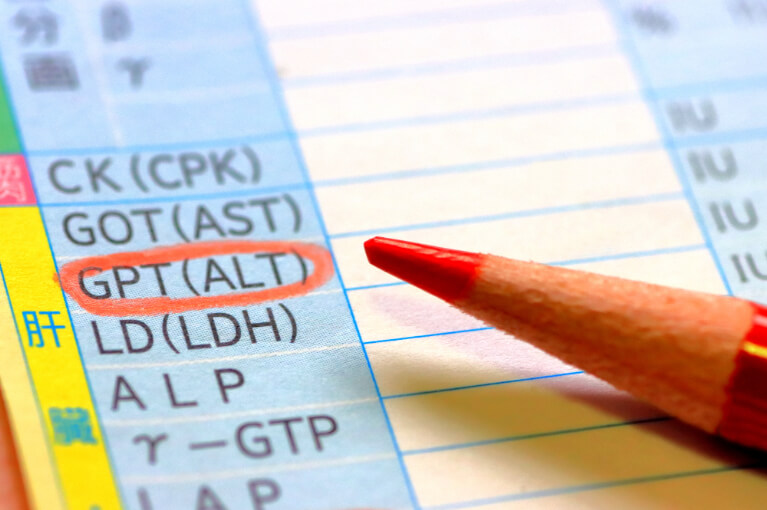 軽症から中等症の場合は自覚症状がないことが多く、健康診断や人間ドックなどで発見されることが多いとされています。
軽症から中等症の場合は自覚症状がないことが多く、健康診断や人間ドックなどで発見されることが多いとされています。
初発症状としては、倦怠感が多く、黄疸や食思不振といった症状が出現することもあります。
肝硬変へ進行した場合、下肢のむくみや黄疸(白目や皮膚が黄色くなる)、腹水、肝性脳症(意識障害)などの症状が出現することがあります。
自己免疫性肝炎の原因
明確な原因は不明です。
血液検査によるものや副腎皮質ステロイドによる治療によく反応することから、自己免疫の関与が考えられています。
また、ウイルス、妊娠・出産、薬物の使用などの後に発症する場合があるため、これらが発症の起因である可能性も指摘されています。
自己免疫性肝炎になりやすい人
自己免疫性肝炎の方は、1型糖尿病や潰瘍性大腸炎などの自己免疫疾患などを罹患している方が多いです。
また、男女による差もあり、約70%は女性とされています。
自己免疫性肝炎の検査と診断基準
健康診断や人間ドックなどで偶然、肝障害を指摘され、その後の精密検査の結果、自己免疫性肝炎と診断されることが多くあります。
診断では、まずその他肝障害の原因で頻度が高い、ウイルス性肝炎や脂肪肝、薬物性肝障害などではないかを確認します。
以下のようなものを検査し診断します。
| 原因 | 治療方法 |
|---|---|
| ・IgG (細菌やウイルスを防御する役目を担っている 免疫グロブリンの一種) ・抗核抗体(自己抗体の総称) |
血液検査で調べます。 自己免疫性肝炎であれば、 IgGの値が高くなり、抗核抗体が陽性となる場合が多い。 |
| 肝生検 | 皮膚上から肝臓に針を刺し、肝臓の一部を取り出して検査を行う。 自己免疫性肝炎であれば、肝細胞に形質細胞(リンパ腫の一種)が多く集まっている様子がみられる。 |
自己免疫性肝炎の治療
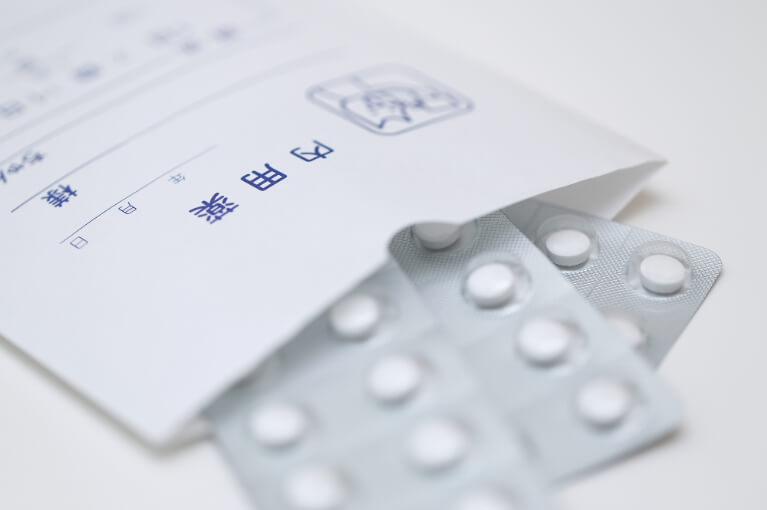 治療の基本は免疫抑制薬の内服です。
治療の基本は免疫抑制薬の内服です。第一選択薬は、副腎皮質ステロイドの内服で、重症度によって開始時の服薬量は異なります。
肝障害の改善がみられれば、服薬量を徐々に減らしていきます。
ただし、中止すると再度悪化することが多いため、少量の副腎皮質ステロイドの内服を長期間継続する必要があります。
なお、副腎皮質ステロイドを服用できない場合や服用を続けても肝障害が改善しないなどの場合には肝機能の改善を促すウルソデオキシコール酸を使用、もしくは併用します
さらに、アザチオプリン(免疫抑制剤)を併用することもあります。
副腎皮質ステロイド服用中は満月様顔貌、糖尿病、骨粗鬆症などが出現する可能性がありますが、専門医の下で適切に治療すれば副作用の発症をかなりの確率で抑えることがあります。
自己免疫性肝炎の食事の注意点
 自己免疫性肝炎だけに向いている特別な食事内容といったものはありません。
自己免疫性肝炎だけに向いている特別な食事内容といったものはありません。
進行した肝硬変でなければ、適度な摂取カロリーでバランスのよい食事を心がけてください。
また、よほど症状が進めば肝硬変が進行すると腹水の出現や栄養状態が悪化します。
塩分や水分制限だけでなく、就寝前の分岐鎖アミノ酸製剤の服用を含めた夜間食(200キロカロリー程度)も栄養療法の一つとされています。早めの受診で診断、治療に入ればその可能性を大幅に下げることが出来ます。
食事に関して疑問があれば、担当医師や管理栄養士に確認してください。
自己免疫性肝炎は完治する?寿命は変わる?
現時点では、完治は難しいとされています。
ただし、早期発見と適切な治療を続けることで、多くの方で肝炎を改善して、病状の進行を抑えることができています。
治療は免疫反応を抑える薬を使用するため、副作用がありますが、症状によっては他の薬で代用することも出来るために副作用を避けることが出来る場合も多いです。
免疫抑制剤を使う場合でも専門医の下で治療を行えば副作用を予防することがかなりの確率で出来ます。