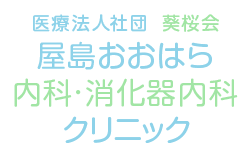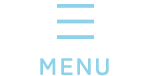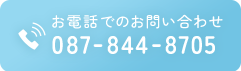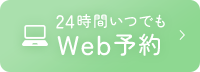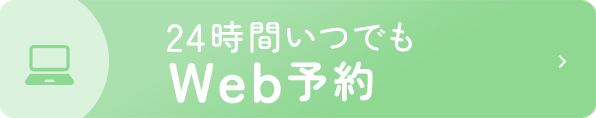日本人の3人に1人が「脂肪肝」
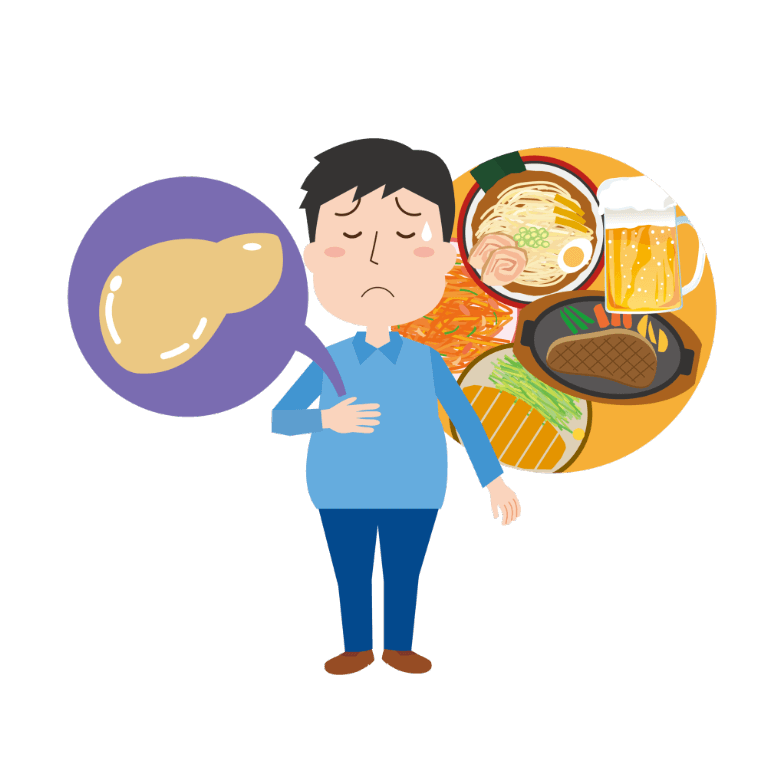 肝細胞に脂肪が蓄積していき、全肝細胞の30%以上が脂肪化している状態のことを「脂肪肝」と呼びます。
肝細胞に脂肪が蓄積していき、全肝細胞の30%以上が脂肪化している状態のことを「脂肪肝」と呼びます。
肝臓では、エネルギー源として作った脂肪を肝細胞の中に溜め込んでいるのですが、作られた脂肪の方が消費エネルギーよりも多いと、肝細胞に脂肪が蓄積していくことになるのです。
食生活の欧米化に伴い年々増加している生活習慣病の一つで、日本人の3人に1人が「脂肪肝」とも言われています。
脂肪肝の症状
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれており、自覚症状はほとんどありません。
しかし、脂肪肝との診断を受けた方は、自覚症状がなかったとしても、着実に肝臓に脂肪が蓄積しており、少なからず肝臓の働きが悪くなっている恐れがあります。
やがて肝炎を起こし肝硬変に進行することもあるため、手遅れになる前に早めに対策をすることが重要です。
脂肪肝の原因
アルコールの多飲が原因になる脂肪肝とそれ以外が原因になる脂肪肝があります。
アルコール性脂肪肝
アルコールの多飲が原因になることもあり、アルコールが原因の脂肪肝を「アルコール性脂肪肝」といいます。
体内に入ったアルコールのほとんどは肝臓で解毒され、体外へ排出されるのですが、その過程で肝臓の働きが低下し、脂肪が溜まりやすくなってしまい「アルコール性脂肪肝」になります。
お酒を飲まないのに脂肪肝?
お酒を飲まなくても、肥満や脂質異常症、糖尿病などが原因で脂肪肝になることもあります。
アルコール以外の原因で生じる脂肪肝を「非アルコール性脂肪肝」といいます。
このような方々は、インスリンの効きが悪くなっている方も多く、効きが悪いと肝臓に脂肪が蓄積しやすくなるため、脂肪肝になりやすいとされています。
脂肪肝の検査と診断
まずは、血液検査や腹部超音波検査、CTなどの検査を行います。
脂肪肝の診断基準
肝細胞の30%以上に中性脂肪が蓄積している場合に診断されます。
以下のような検査を行います。
| 検査 | 概要 |
|---|---|
| 血液検査 | 肝臓に障害が起こると上昇する ALT(GPT)、AST(GOT)の値が上昇します 非アルコール性脂肪肝はALTが高くなりやすく、アルコール性脂肪肝はASTが高くなりやすいとされています。 腹部超音波検査 腹部超音波検査では脂肪肝は白っぽく映ります。 |
| 腹部CT検査 | X線を使用して体の断面図を撮影できる検査です。 脂肪肝になると肝臓が他の臓器と比較して黒く映し出されます。 |
脂肪肝が進行している時
脂肪肝は、肝炎を起こし肝硬変に進行することもあり、この場合、掌の両側(親指と小指の付け根)が赤くなる「手掌紅斑」、下腹部に水が溜まる「腹水」、皮膚や白目が黄色くなる「黄疸」などの症状が出現します。
脂肪肝を治す方法
軽度の脂肪肝であれば、比較的容易に改善できる可能性があります。
生活習慣が原因とされる場合は、食事療法や運動、禁酒などを行って肝臓に蓄積した脂肪の減少を図りましょう。
脂肪肝の人が控えるべき食べ物
 まずは、糖質に気をつけなければなりません。
まずは、糖質に気をつけなければなりません。
日常的な糖質の過剰摂取は、脂肪肝になりやすいことがわかっています。
また、普段の食事に気を付けていても、間食も考えて摂らないと意味がありません。
間食といえば、菓子やジュース、果物ですが、これらは糖質が多い食べ物です。
摂取量には注意しましょう。
脂肪肝が改善する食生活
 バランスのとれた食事とは、「主食1品」「主菜(魚、肉、卵、大豆製品など)1品」「副菜(野菜、きのこ、海藻類)2品」の形です。
バランスのとれた食事とは、「主食1品」「主菜(魚、肉、卵、大豆製品など)1品」「副菜(野菜、きのこ、海藻類)2品」の形です。
このような食事を1日3食摂るようにします。
主食や主菜が2品以上になるとエネルギーが過剰になるため避けてください。
また、食物繊維は、低エネルギー食品であるとともに糖質や脂質の吸収を遅らせます。
運動療法
 運動によって、肝機能障害や肝臓の脂肪化の改善が期待できます。
運動によって、肝機能障害や肝臓の脂肪化の改善が期待できます。
また、肥満を合併した脂肪肝の方が、30〜60分の有酸素運動を週3〜4回行い、4〜12週継続すると、たとえ体重が減らなくても肝臓の脂肪化の改善が見込めることがわかっています。
運動は脂肪肝だけでなく他の生活習慣病の改善や予防にもなります。
できる範囲で積極的に取り組みましょう。